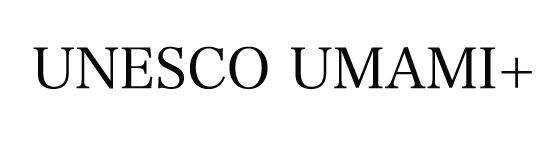秋の旅プラン:八幡
|
9月、厳かなる王朝の祭り、石清水祭! 茶室で見つめる、儚きいのちの行方。平安期 年間に東北の大震災はじめ天災が多発。厳かなるものの質感に出会う旅 |
-
 八幡市立松花堂庭園・美術館
八幡市立松花堂庭園・美術館
住所:京都府八幡市八幡女郎花43
Tel:075-981-0010茶庭は、東車塚古墳の上にあり、松花堂昭乗自らの手による造園といわれる。庭の中心部は、古墳前方部の平坦なところを利用して造られ、灯篭や立ち木を除いて空間をつくり、地に這う潅木と巧みな飛び石の配置し、それを埋める苔によって平面の美が構成されている。「寛永の三筆」の昭乗は絵も描いた。日本絵画の伝統である平面の構成性をよく知っていた。
-
 男山四十八坊跡 石清水八幡宮
男山四十八坊跡 石清水八幡宮
住所:京都府八幡市八幡高坊30
Tel:075-981-3001明治期までは神仏習合で石清水八幡宮の本殿では読経が流れ、社僧という僧侶が社務を取り仕切った。昭乗は社僧である。男山には48もの坊と呼ばれる寺があった。大阪・堺の出身の昭乗は、石清水八幡宮で出家をし、瀧本坊の社僧となり、その住職となる。参道の石垣と本殿前の参道に並ぶ石燈籠。燈籠の竿の部分には、宿坊のそれぞれの坊名が刻まれる。
-

石清水
祭(石清水八幡宮)
住所:京都府八幡市八幡高坊30
Tel:075-981-3001葵祭の北祭に対し都の南祭。王朝文化を現代に伝える正統的祭祀、文化と歴史の動く古典である。貞観5(863)年旧暦8月15日、男山の裾を流れる放生川(ほうじょうがわ)に魚を放す「石清水放生会(ほうじょうえ)」がはじまり。平安期の貞観(じょうがん)年間は、東北の震災はじめ全国各地に天災が多発した。はかなき生命(いのち)に目を向けるその意味は、今も何も変わってはいない。