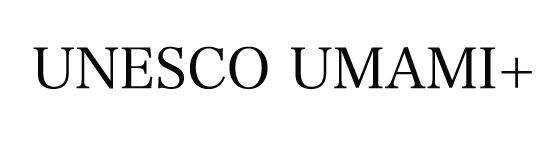ブック+
|
著 者:重森三玲 出版社:河原書店 |
森三玲(1896−1975)は、日本画を学び、お茶や生け花に通じた日本を代表する作庭家。京都の東福寺方丈庭園などの代表作がある。枯山水とは、水を用いずに、石砂などにより風景を表現する庭園様式で、室町時代中国の山水画の影響を受けて完成された。15個の石を一見無造作に5か所、点在させただけのシンプルな京都の龍安寺の石庭は有名である。枯山水の庭は、水を用いないことでより水の質感をひとに感じさせる。日本人の究極の「引き算の美学と思想」を表している。グランシェフは、世界中の素材をふんだんに使いながら、じつは引き算をしている。そしてエレガントな料理を仕上げる。日本の枯山水の美学とグランシェフの料理のエレガンスには、かさなり通じるものがある。1906年ニューヨークで、英語で「茶の本」を出版した岡倉天心は、われわれは「不完全」に対する真摯な瞑想をつづけているものたちなのであると語っている。UMAMIを追求する現代のグランシェフもまた、「不完全」な料理の中に、躍動するUMAMIを感じ続けている。水もUMAMIも動体で、流体。ひとが持ち得る質感で追い続けるしかない。庭も料理もそれを支え保つ器ともいえる。
 龍安寺石庭幅
龍安寺石庭幅約25m、奥行き約10mに白砂を敷き詰め、砂紋をつけ、15個の石を点在させた石庭を持つ龍安寺は京都北山、衣笠山の麓に位置する。宝徳2年(1450)、室町幕府の管領、細川勝元が藤原北家の徳大寺家の山荘を譲り受けて禅寺を創建。初代住職には、妙心寺住持の義天玄承(玄詔)を迎える。臨済宗妙心寺派に属し大雲山と号し禅苑の名刹である。
 東福寺方丈庭園作
東福寺方丈庭園作庭家重森三玲の代表作がある京都・東福寺。鎌倉時代、九条道家が奈良の東大寺、興福寺の各1字を取り寺名とし創建の京都五山第四位の禅寺である。そして当寺の禅宗方丈庭園は異色を放つ。鎌倉期の質実剛健な風格を基調に、現代作家、重森三玲がモダンアートの抽象的構成を取り込む。日本画を学び、お茶や生け花に通じ、日本庭園史を研究した三玲の庭は、力強い石組みとモダンな苔の地割りが特徴。思想を意匠化し空間性を高める。