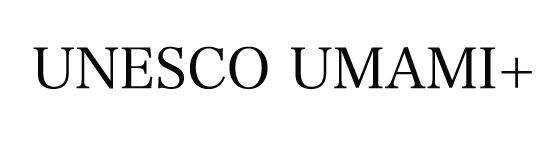世界遺産+
カンボジア・プレアヴィヒア寺院
Temple of Preah Vihear
Temple of Preah Vihear
Province Siem Reap
ク
メール王朝拡大の拠点
4世紀北インド全域を支配する大王国グプタ朝が登場、5世紀にインド船交易を通じ東南アジアにインド化が広がる。6世紀メコン川中流域にクメール族がヒンドゥー教の影響の強いカンボジアを建国し、仏教が盛んな扶南を滅ぼす。プレアヴィヒア寺院は、カンボジア・タイ国境ダンレク山地の断崖上にあり、9世紀からクメール王朝が建造したヒンドゥー教寺院。東西の春秋分線ではなく、タイ国境線の北を南の頂上から見下ろすように伽藍が立つ。
©2013 UNESCO
 新
新潟・上越にあり上杉謙信が居城とした春日山城は、越後の地域支配と外部からの侵攻に対抗するための拠点として、要害の地に支城、砦、館が配置されていた山城。山中には春日山城と支城・砦を結ぶ軍事用道路があった。また天徳2(958)年に山頂付近に奈良の春日神社を勧請したことで山名となる。当城は、山の宗教施設と城塞がかさなる南北朝につづく。
 新
新潟にある標高634m弥彦山の山麓に、越後開拓の神アメノカグヤマノミコトを祀り、上杉謙信はじめ多くの武将に信仰された神社。宮中で11月の新嘗祭の前日に行われる鎮魂祭を、奈良の石上神宮と同じように行う神社である。大和朝廷は奥州への進出を日本海から北上した。またそれは大陸伝来の最新の農業システムと暦をともなう思想の北上でもあった。
 新
新潟・村上の日本海に面する丘陵にあり、大化4(648)年の蝦夷征伐の前線基地として磐舟柵が置かれた頃には、既に石の祠が祀られていた歴史を持つ。9世紀には北陸道観察使秋篠朝臣安人が京都・北山の貴船神社を勧請する。古代の城柵は単に城塞ではなく、最新の農業システムと暦をともなう思想を実践する区画をもつもので、都市に近かった。