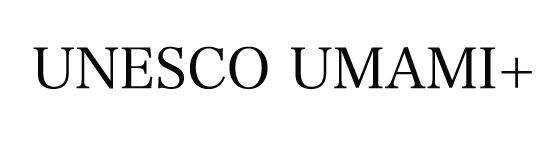世界遺産+
インド・ブッダガヤの大菩提寺
Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya
Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya
State of Bihar, Eastern India
7
世紀 東アジアのインド化を語る
釈迦が悟りを開いた場所で、古代インドを統一したマウリア朝のアショーカ王(BC268年頃—BC232年頃)が寺院を建立する。高さ52mの大塔は、7世紀に訪れた中国の三蔵法師玄奘の記録に登場する。インドがイスラーム王朝に支配され12世紀に大菩提寺が放棄される際、最後の僧侶たちは、大塔が破壊されることを恐れ、塔の大半を土で覆い隠した。仏教聖地のシンボルであり、古代インド石造建築を伝える高い価値を持つ。
©2013 UNESCO
 京
京都四条通りの東のつきあたり、円山公園と隣接し、地元の氏神、産土として信仰をあつめ、7月の祇園祭りで有名な神社。その歴史は7世紀渡来僧により釈迦が説法を行う祇園精舎の防疫の神、牛頭天王を祀ることからはじまり、祇園祭は9世紀都の疫病防疫の祭礼にはじまる。7月1日の「吉符入」から31日の「疫神社夏越 祭」まで、1ヶ月にわたり神事・行事がくり広げられる。
 滋
滋賀・草津の湖岸烏丸半島にある日本最大規模の湖をテーマにする博物館。水族館を持ち、琵琶湖固有種がすべて見られ、国内外の淡水魚も展示され、生きたプランクトンも観察できる。琵琶湖とひとのくらしの関わりもわかりやく紹介される。7世紀以降インド文化・文明が伝来し日本文化にとけ込む。琵琶湖もインド河神・河畔神弁才天が持つヴィーナ・琵琶に由来。
 長
長野・上田にあり、奈良時代に奈良・東大寺と結ばれた国分寺ネットワークの寺院。本寺は信濃国分寺跡から北300mに位置し、薬師堂の本堂、仏塔、鐘楼、観音堂、大黒堂で伽藍を構成する。地域の蘇民講の人達による手作りの絵入り蘇民将来の御符が毎年1月に授与、販布されている。蘇民将来の御符は、疫病を除いて福を招くとされ、インドの牛頭天王に由来する。